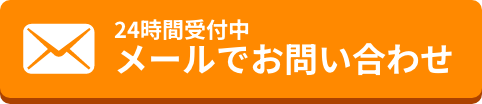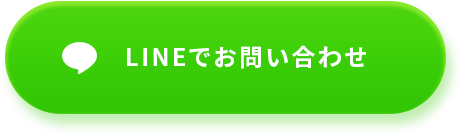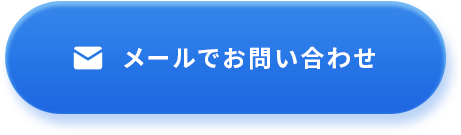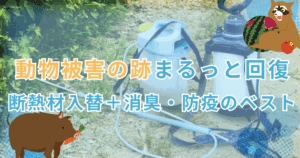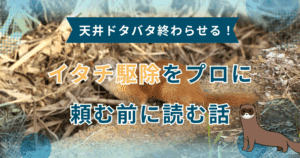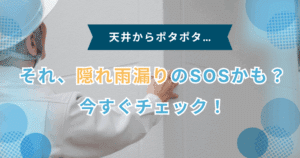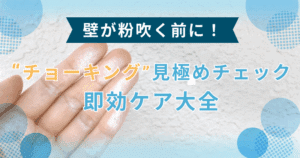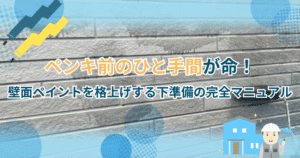家じゅうムシムシ…それ、雨漏りかも!?今すぐできる見逃しゼロチェック
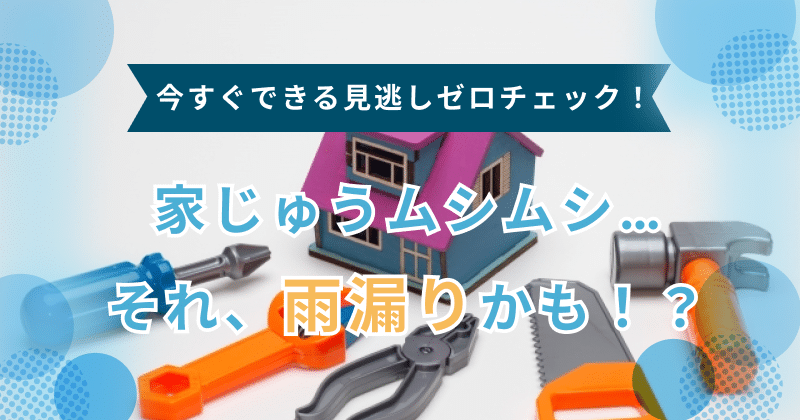
室内でしっかり除湿しているのにジメジメ感が続いたり、カビやダニの増殖が止まらない場合、住宅の見えない部分で湿気が発生している恐れがあります。特に雨の多い季節は、雨漏りが原因で家全体の湿度が上がっている可能性があります。雨漏りは屋根や外壁から侵入した水分が壁内や天井裏に留まることで、室内環境に影響を与えます。今回は、雨漏りが室内湿度を高める理由と、放置することで生じる二次被害について詳しく解説します。
雨漏りがあると家全体の湿度が上がる?

近年は、高い気密性を持つ住宅が増加しています。こうした住宅は、断熱材や防湿シートで家全体を覆い、室内外の空気の出入りを抑えて快適な環境を保つように設計されています。しかし、雨漏りが起こると問題が発生します。屋根や壁から侵入した雨水は、天井に達する前に屋根裏や壁内の断熱材などに吸収されてしまいます。
本来であれば、吸収した水分が自然に乾燥すれば問題ありませんが、屋根裏や壁内部は日が当たらず、湿気がこもりやすいため、乾燥はほとんど期待できません。雨漏りが繰り返されると、断熱材や建材に含まれる水分は徐々に増え、最終的には溜まった水分が湿気となって室内に放出されるようになります。
こうして湿度対策をしても家全体がジメジメする原因となり、快適な室内環境を保つのが難しくなります。さらに、雨漏りによる湿度上昇はすぐに室内に変化が現れるわけではないため、湿気の原因が雨漏りだと気づきにくい点も注意が必要です。
雨漏りを早く見つけるためのポイント

雨漏りと聞くと、多くの方は「天井から雨水がポタポタと落ちてきてバケツで受け止める」ような状況を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、その状態は雨漏りがかなり進行した末期の症状であり、すでに屋根裏などで建材の腐食やカビ・ダニの増殖が進んでいる可能性が高いのです。
雨漏りを早期に発見して被害を最小限に抑えるためには、初期症状を見逃さないことが大切です。例えば、天井や壁のクロスが浮いていたり剝がれていたりする場合や、クロスにシミや変色、黒カビが見られる場合は、雨漏りの初期症状の可能性があります。
さらに、外壁のひび割れや、建物の隙間を埋めるコーキングが劣化していることで、窓枠にシミができたり、窓サッシを固定するネジが錆びているなどの症状も要注意です。これらは一見すると結露のように見えることもありますが、そもそもその結露自体が、雨漏りによる断熱材の劣化が原因になっているケースもあります。
いずれにしても、これらの異変は住宅の不具合を示している可能性があるため、気づいた時点で早めに専門業者などに依頼して住宅全体の点検を行うことをおすすめします。
雨漏りによる二次被害は危険

雨漏りによる二次被害は、ある日突然発生するわけではありません。しかし、家全体が高湿度の状態に長期間さらされることで、さまざまな深刻な被害を引き起こす恐れがあります。
まず、住宅全体の湿度が高い状態が続くと、カビが非常に発生しやすくなります。カビは断熱材や木材などの建材を腐食させるだけでなく、ダニの発生を促す原因にもなります。そして、カビやダニはアレルギーを引き起こす可能性が高く、放置してしまうと家族の健康被害に繋がりかねません。
さらに、雨漏りで湿った木材はシロアリにとって格好のエサになります。実際、シロアリ被害の多くは雨漏りが原因で起こっており、これにより住宅の耐久性が大幅に低下することもあります。つまり、雨漏りは健康被害だけでなく、住宅の寿命そのものにも大きな影響を与えてしまうのです。
特に、壁の中やコンセント周辺からカビ特有の土のような臭いがする場合は、目に見えない部分でカビが広がっているサインです。こうした異変に気づいたときには、被害が拡大する前に住宅全体を専門業者に調査してもらい、必要な補修や対策を早めに講じることが重要です。
まとめ
今回は雨漏りと住宅の湿度、そして雨漏りによって引き起こされる二次被害についてお話ししました。家全体がなんとなくジメジメしていると感じたときは、壁紙にシミや浮きがないか、カビが発生していないかなど、家の中を隅々まで確認してみてください。
なお、シミは結露によっても発生するため、雨漏りかどうかの判断が難しいケースもあります。自分で見極めができない場合は、迷わず専門業者へ相談することをおすすめします。
雨漏りを放置すると、カビの発生や住宅の劣化を招くだけでなく、湿気を好むダニやシロアリといった害虫、さらにはネズミなどの害獣を引き寄せてしまう可能性もあります。雨漏りの兆候を見つけた際には、被害が広がる前に必ず点検を行い、必要に応じて修繕を進めましょう。