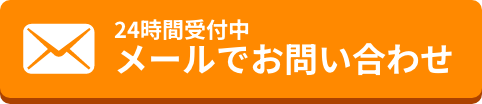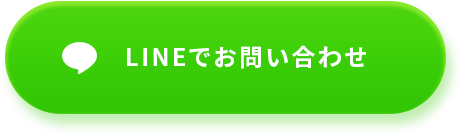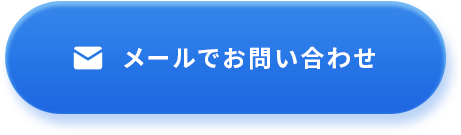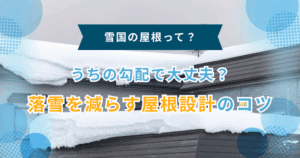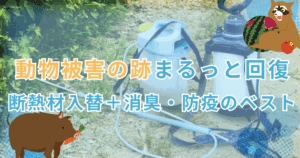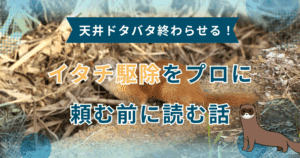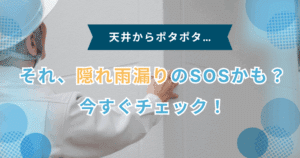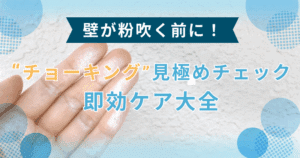うちの勾配で大丈夫?落雪を減らす屋根設計のコツ
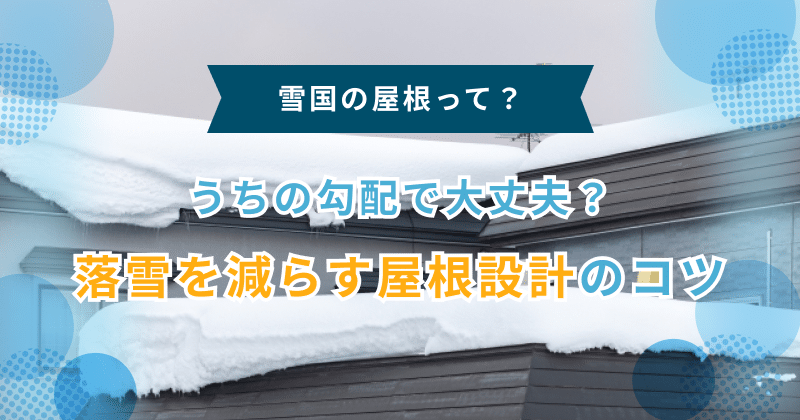
日本は南北に長く、温暖な地域から厳寒地まで気候の幅が大きい国です。なかでも降雪の多いエリアでは、屋根に積もる雪が住宅への負担となり、落雪による思わぬ事故を招くおそれがあります。
こうした雪害を減らすため、積雪地域の住宅では屋根の形や勾配に独自の工夫が施されています。雪の重みや落下の危険を見据えた設計にすることで、日常の安全性を高める取り組みが行われているのです。
雪国の家はどんな屋根?
雪国の屋根には、大きく分けて次の3種類があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
❄️ 落雪式屋根
屋根の勾配を急にして、自然に雪が滑り落ちるように設計された屋根。雪下ろしの手間を軽減できますが、落雪による安全対策(落下防止柵や消雪設備)が必要です。
💧 融雪式屋根
電熱線や温水パイプを使って屋根の雪を溶かす方式。雪を落とさないため隣家や道路への落雪リスクが少なく、都市部の住宅で採用されやすいです。ただし光熱費や設備維持費がかかります。
🏔 耐雪式屋根
頑丈な構造で、屋根の上に雪をためて支える設計。雪が断熱材代わりになり、室内の保温効果もあります。雪下ろしの手間を減らせますが、建築コストが高くなります。
➡️ いずれも雪国には欠かせない方式で、地域環境や暮らし方に応じて選ばれています。
落雪式屋根

落雪式屋根は、勾配を大きく取って雪が自重で滑り落ちるよう設計された屋根です。
白川郷の合掌造りのようにしっかりと傾いた屋根を思い浮かべると分かりやすいでしょう。豪雪地では屋根に雪をため込まないことが重要で、この形状により建物へかかる荷重を軽減できます。
一方で、名前どおり雪が滑り落ちるため、落雪による影響には注意が必要です。安全に雪を受け止められるよう、庭などの広いスペースを確保しておくことが求められます。
融雪式屋根

融雪式は、屋根に積もった雪を熱で溶かして処理する方式です。
ガスや電気を使って屋根そのものを温めるため、落雪式や耐雪式に比べてランニングコストやメンテナンス費用がかかります。
その一方で、敷地が狭い家でも導入しやすく、雪を落とす必要がないぶん安全性が高いのが利点です。雪下ろしのために屋根へ上がる必要がなく、隣家へ雪を落として迷惑をかける心配もありません。
耐雪式屋根

耐雪式は、屋根上に雪を乗せたままでも耐えられるよう、建物自体の強度を高めて設計する方式です。鉄筋コンクリート造や鉄骨造を採用し、一般的な戸建てより躯体を頑丈にします。敷地にゆとりがない場合でも、落雪スペースを気にせず計画できる点がメリットです。耐雪式屋根には次の2タイプがあります。
スノーダクト方式
屋根にわずかな勾配を設け、中央に設置したダクトへ雪解け水を集めて外部へ流す方法です。勾配を中央側に取るため、つららが生じにくいのが特徴です。
フラットルーフ方式
屋根面をほぼ水平にして積雪をそのまま保持する方法です。降雪量が多くなければ、自然に融けて水として流れます。大雪時には屋根への負担が大きくなるため、定期的な雪下ろしが必要です。
屋根以外にも、家づくりの工夫は色々!
雪国では、屋根の形状だけでなく住宅全体にさまざまな対策が施されています。
たとえば床の位置を高くする高床式住宅にすることで、豪雪時でも窓が雪で埋もれにくいよう配慮します。積雪が2メートルを超える地域でも、こうした工夫で生活への支障を抑えられます。
二重窓

窓は室内の熱が最も逃げやすい部分です。暖房で温めた空気を無駄にしないため、窓を二重にして寒さ対策を行います。二重化によって、せっかくの暖気が外へ逃げるのを防ぎます。
さらに、カーポートや倉庫、車庫など、屋根に雪が積もる構造物には、雪の重みに耐えられるよう荷重対策が一通り施されています。
屋根からの落雪は重大なリスク
積雪地域では、屋根から滑り落ちる雪が大きな危険につながります。歩行者や車両への影響といった安全面はもちろん、隣家の敷地へ雪が落ちることでトラブルを招くおそれもあります。
雪下ろし作業は事故につながりやすい
| 分類 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 雪下ろし・除雪作業中 | 95人 | 約86% |
| その他の雪害 | 15人 | 約14% |
| 合計 | 110人 | 100% |
消防庁の『令和3年版 消防白書』によると、2020年11月〜2021年4月の雪害による死者は110人で、そのうち屋根の雪下ろしなど除雪作業中の事故が95人と、全体の85%超を占めています。
雪下ろしをする本人が屋根から転落する危険だけでなく、落とした雪の塊が家族や近隣の方に当たるリスクも無視できません。
それほど雪下ろしは危険度の高い作業です。とくに高齢の方は、可能であれば作業を避けるのが賢明でしょう。あわせて、屋根の仕様を見直して落雪対策を講じることも検討してみてください。
隣家とのトラブルに発展することがある
積雪地域では、屋根から滑り落ちた雪が原因で隣家とのトラブルが起こり得ます。隣地の敷地へ雪が落下して物損が発生することがあり、状況によっては人身事故に至るおそれもあります。
雪の重さは1立方メートルあたり約300〜350キログラムといわれ、100キログラムを超える落雪も珍しくありません。落雪は屋根から雪を落とした人の責任となるため、雪国向けの屋根仕様で対策を講じておきましょう。
なお、落雪式屋根の場合は、降雪時に屋根の真下へ近づかないよう注意が必要です。
雪国の屋根は定期メンテナンスが肝心

積雪の影響を受けやすいため、雪国の屋根は他地域に比べて劣化が早まる傾向があります。だからこそ、定期的な点検・手入れを欠かさないことが大切です。なお、必要な対策は採用している屋根方式ごとに異なります。
落雪式屋根は劣化が進みやすい
落雪式屋根は、雪を自重で滑り落とす形状です。雪が落ちる際に塗膜も一緒に削られやすく、結果として屋根の傷みが早く進みます。そのため、メンテナンスの間隔は短めに設定する必要があります。
目安として、一般的な住宅なら約10年ごとに実施する屋根塗装を、落雪式では約8年で行うイメージです。
また、湿度85%以上・気温5℃以下の環境では塗料が密着しにくく、降雪期の塗装は適しません。雪のない時期を選び、計画的にメンテナンスを進めましょう。
耐雪式屋根は定期清掃bが欠かせない
耐雪式屋根は屋根上に雪を載せる前提のため、雪下ろし作業が必要になるというデメリットがあります。加えて、ほかの方式に比べて勾配がない、または緩やかなことが多く、屋根面に付着した汚れが流れ落ちにくいため、清掃の手間がかかります。
また、雪国特有の「すが漏り」が起こる可能性もあります。これは、屋根上部にたまった水が凍結して排水できなくなり、行き場を失った水が雨漏りのように室内へ侵入してしまう現象を指します。